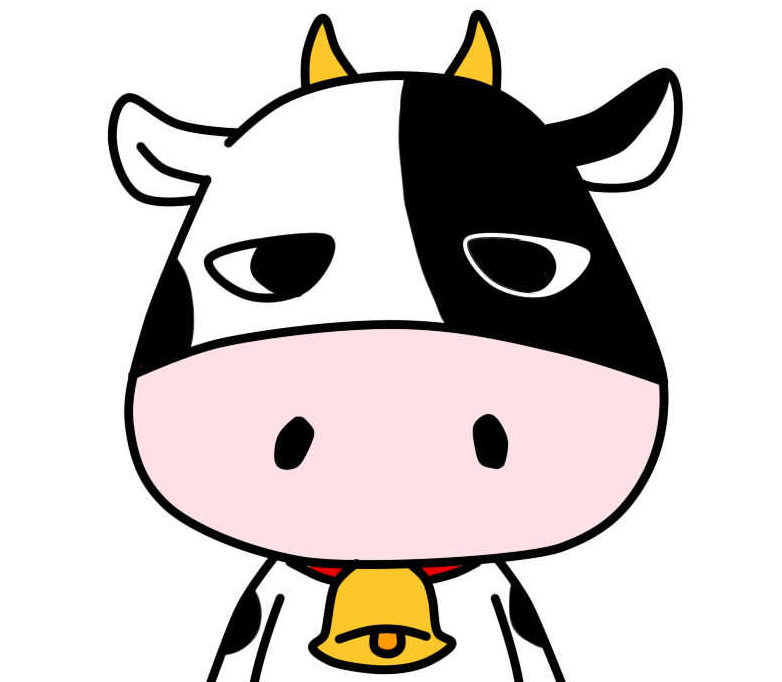焼肉の定番といえば「カルビ」。そんな焼肉やBBQなどで日頃よく食べられている「カルビ」ですが、実はその定義は少し曖昧で、様々な特徴をもつバラ肉を大きくまとめて「カルビ」と呼んでいます。
少し高級な焼肉屋さんでは、ササバラやカイノミ、ザブトンなど聞きなれない部位も多くありますが、これもすべてカルビに含まれています。
今回はそのような細かいカルビの部位について詳しく解説し、ロースやハラミとの違い、カルビをおいしく味わうための焼き方や飲み物など、これを読めばカルビのすべてが分かるようまとめてみました。是非、参考にしてみてください。
カルビを知るには焼肉文化のはじまりを知ろう

そもそも“焼肉”とはいつから日本に伝わったのか知っていますか?その始まりは朝鮮半島(いまの韓国ですね)を日本の領土にしていた1933年頃がはじまりと言われています。ちなみに当時の韓国では、焼肉といえば牛肉ではなく、豚肉が基本だったそうです。
今では日本同様、様々な部位のお肉を楽しむことが出来る韓国の焼肉店も、その当時はカルビ専門店やミノ専門店など、一つの部位しか取り扱わないのが一般的でした。
なので、カルビやタン、ハラミといった様々な部位を味わう現在の焼肉スタイルは、日本独自のアレンジによって生まれたということになります。
その証拠に、日本初の焼肉店は1946年に新宿にオープンした「明月館」と言われており、1950年代にはカルビもロースもミノもすでに食べられていたそうです。
このことからも一見古くからありそうな焼肉文化も、その歴史はまだまだ浅くとても新しいのなのです。
カルビとは一体なにを意味するの?

さて前置きが長くなりましたが、そもそもカルビとは何なのかをまず最初にお伝えできればと思います。
カルビの語源はモンゴル語で「qarbing(下腹)」という意味から来ているという説や、韓国語で助骨(あばら)を意味する言葉が由来とも言われています。
焼肉大国の韓国では、日本のように「カルビ=焼肉」という訳ではなく、様々な料理に使われています。
例えば、鶏と野菜をコチュジャンで炒めた「タッカルビ」、豚肉を醤油ベースのタレでつけて焼く「デジカルビ」、カルビのお鍋「カルビタン」などその種類は豊富にあります。
View this post on Instagram
カルビは肉全般を指す意味で様々な料理に使われている名前で、韓国語だと「肋骨(あばら)周辺」の肉を指す
細かいカルビの部位について
そんなざっくりした意味で使われる「カルビ」ですが、細かく見てみると実はいくつもの部位に分かれています。例えばあばらの近くにある肉であれば、基本的にどの部位もすべて「カルビ」となるのですが細かな部位の違いによって特徴や味わいが異なります。
「カルビ」は大きく”かたばら””ともばら”の二つに分ける事ができる

とても細かな話をしますが、まずカルビというのは大きく2つのカルビに分けることができます。それが「かたばら」というカルビと「ともばら」というカルビです。
- 肩に近い部位の【かたばら】・・・肺に近く筋肉質のため、硬めの肉質。
- 後ろ足の付け根の部位【ともばら】・・・一般的なカルビはこの部位となる
”かたばら”は3種、”ともばら”は4種に分類される

またまたとってもややこしいのですが、この「かたばら」と「ともばら」はそれぞれもっと細かい名称に分けられます。
①三角バラ
②ブリスケット
③ザブトン
①かたばら系に属しているカルビ【三角バラ】
この三角バラは牛の第1~6助骨部分を三角形に切った部位で、牛一頭からわずか2枚しか取ることができない希少部位です。
ほど良い霜降りの赤身肉で、味は濃厚、一口食べた瞬間、その旨味が口の中に一気に広がります。
カルビの中では超レアなお肉で「一番おいしい!」と言われている部位です。お店で見かけた際は、少し奮発してでも一度は食べてみることをオススメします。
View this post on Instagram
②かたばら系に属しているカルビ【ブリスケット】
前足の付け根辺りにある肩バラの赤身肉。少し硬めの部位なので、使える部分は全体の1~2割ほどで、希少部位とされています。
味が非常に濃いのですが、比較的あっさり食べられるのが特徴です。焼肉店でもお家でも薄くスライスして食べるのがオススメです。
③かたばら系に属しているカルビ【ザブトン(ハネシタ)】
肩ロースの一部にあたる部位なのですが、背中側ではなく、あばらに近い所にあります。きめ細かいサシやとろけるような味わいが人気の希少部位です。
ザブトンやハネシタという名称で呼ばれ、店によっては特上カルビとして提供されている最高級部位です。また焼肉以外にもしゃぶしゃぶやすき焼き、ステーキにしてもとても美味しくいただけます。
View this post on Instagram

①カイノミ
②インサイドスカート
③ササバラ
④タテバラ
ともばら系に属しているカルビ【カイノミ】
カイノミは背中側のヒレに近い部分にある「中バラ」と呼ばれる部位で、ヒレと隣り合うだけあってバラの持つ上質な甘みやコク、ヒレの特徴でもある非常に柔らかい赤身肉の食感と、両方をバランス良く持ち合わせているお肉です。
その形が貝に似ている事からその名が付けられたと言われています。一頭から左右1ブロックずつしか取れない希少部位で、特に焼肉との相性が最高です。塩でもタレでも何を付けてもよく合います。
View this post on Instagram
ともばら系に属しているカルビ【インサイドスカート】
カイノミが背中側の部位に対し、このインサイドスカートはお腹側の「外バラ」と呼ばれる、横隔膜のハラミに近い部分をさします。
味わいもカルビの旨味とハラミのさっぱりさの両方を兼ね備えており、とても食べやすい希少部位です。内臓肉のハラミを英語で「アウトサイドスカート」と呼ぶのも、インサイドスカートが隣り合う部位であることが関係しているのかもしれません。
インサイドスカートという名前は、アメリカのカットの規格がそのまま使われている珍しい部位となっています。別名ウチハラミと呼ばれることもあります。
ともばら系に属しているカルビ【ササバラ】
このササバラは切った時に、笹の葉に似ている事からこの名が付いたと言われています。インサイドスカートと同じ「外バラ」の一部ですが、部位の場所はモモの付け根に近く、別名ササミとも呼ばれています。
肉質はキメが細かく脂肪と赤身のバランスが良いのが特徴です。一見こってりとしていそうなくらい脂質が綺麗に入っていますが、食べてみると意外とあっさりとしていて、くどさは感じられません。
あまり焼き過ぎると硬くなってしまうので、表面をさっと焼いてレアで食べるのがオススメです。
ともばら系に属しているカルビ【タテバラ】
タテバラはあばら近くの体の外側に沿って取れる部位です。お店では「並カルビ」として提供されている所も多く、一度は食べたことがあるかもしれません。
他の部位に比べ、非常に脂が多く、濃厚なので、こってりとしたお肉が好きな方にはオススメです。脂の多さが苦手な方には、レモンやわさび醤油で食べるとさっぱりと食べられます。
焼肉屋で目にする上カルビや特上カルビ、中落ちカルビって何?


ここまでカルビの細かい部位についてお伝えしましたが、ぶっちゃけ細かい部位の名称ってなかなか目にすることがないかと思います。
実際に目にするカルビの名前は「上カルビ」や「特上カルビ」「中落ちカルビ」などの名称ですよね。そこで次はそういった焼肉屋などでよく目にする名称の肉がどういうもので、どんな違いがあるのか?を解説したいと思います。
上カルビや特上カルビについて


店でよく見かける「上カルビ」や「特上カルビ」はハラミやヒレのように、決まった部位の名称ではありません。
柔らかく脂の乗りが非常に良かったり、綺麗なサシが入っていたりと良い状態のバラ肉であれば、お店の判断で「上カルビ」や「特上カルビ」と決められ、提供されている事が多いそうです。
例えば上カルビにはカイノミ、特上カルビは三角バラやササバラ、ザブトンというようにカルビの中の希少部位が使われることが多いようです。
中落ちカルビについて


中落ちカルビは「特上カルビ」や「上カルビ」と違い、おおよそ使われる部位が決まっているのが特徴です。
中落ちカルビは助骨と助骨との間にある非常に脂がのっている部位のことを言います。「ゲタカルビ」と呼ばれることも多く、このゲタカルビに骨が付いているものは「骨付きカルビ」と呼ばれています。
骨の間の部位のため、あまり多くは取れませんが、牛のランクによっては比較的リーズナブルに食べる事ができます。
カルビはロースやハラミとは何が違う?


ここまで、カルビについての詳しく解説をしてきました。焼肉の定番メニューとしては他にロースやハラミがありますが、カルビとはどのように違うのか?次はその点に関して解説します。
部位の場所の違いは?
- カルビ・・・肩やあばらの周辺
- ロース・・・牛の背中の全体、肩ロース、リブロース、サーロインなどがこの部分
- ハラミ・・・横隔膜の背中の薄い部分、実は内臓物(ホルモン)に属している
脂質や肉質の違いは?
- カルビ・・・ロースやハラミに比べ、脂質が多く、部位によっては硬めでジューシー。
- ロース・・・脂が適度にのっており、カルビよりはさっぱり、ハラミよりはこってりしている。
- ハラミ・・・もっとも脂質が少なくあっさりしている。肉質は柔らかく、クセがない。
カロリーの違いは?(100gあたり)
- カルビ・・・517kcal(和牛)
- ロース・・・469kcal(和牛リブロース)
- ハラミ・・・342kcal
※ちなみに輸入牛の場合はカルビもロースも100~200kcalほど低くなります
カルビの上手な味わい方
最後にカルビを何倍もおいしく味わうためのポイントをいくつかご紹介しようと思います。是非、焼肉店やお家で焼く際は参考にしてみてください。
カルビのおいしい焼き方


まずカルビのような脂がのっているお肉は、しっかりと脂に火を入れる必要があります。カルビをレア状態で食べてしまうと、体内で脂を溶かす際にたくさんのエネルギーを使ってしまい、その分体に負荷がかかるため、結果、胸やけ起こしてしまいます。
よく「肉は1回しかひっくり返してはいけない」と言いますが、肉マイスターの田辺氏曰く、3ミリ以上の厚みがある場合、トングで何度さわったとしても、肉汁や旨味が逃げる事はないのだそうです。
カルビによく合うタレ


脂が多い肉の場合は、醤油ベースのタレに付けて食べることで、くどさが無くなりおいしくいただけます。また、タレではなく醤油やわさび醤油もおすすめです。
おいしいお肉に力を入れている本気の料理人がいるお店では、“肉の美味さに負けないタレ”を作っている場合が多いそう。お店に行った際はタレにも是非注目してみてください。
カルビに良く合う飲み物


カルビによく合う飲み物としておすすめなのは、「温かいお茶」です。ミネラル豊富で、体に残った脂を流してくれるので、胸やけや胃もたれを防いでくれます。ウーロン茶、マテ茶、緑茶、ブレンド茶などお茶であれば何でもかまいません。
また、肉の消化を助ける飲み物としておすすめなのは、パイナップル、キウイ、マンゴーの「果汁100%ジュース」です。お子様と一緒に食べる際に出してあげると良いかもしれません。
最後に、カルビに合うお酒ですが、赤身肉には「ワイン」や「ビール」などの茶色のお酒がよく合います。合わせる際には“どう肉の脂を生かすのか”が、おいしくいただくカギとなります。
お酒好きの方も、おいしいカルビと合わせる際には度数の低いものを選んだり、水やソーダで割るなどして、肉本来の旨味を味わうようにしてみてください。
カルビについてまとめ


ここまでカルビについて、浅いところから深いところまでまとめてお伝えしました。一口にカルビと言っても細かく細分化されていることがお分りいただけたかと思います。
今回の記事の中ではカルビについて7種類まで細かく分けてお伝えしましたが、実際のところそんなに細かく知っておく必要性はないように思います。笑
ただ、上カルビや特上カルビが何の部位なのか?またカルビに合う飲み物って何なのか?そのあたりを知っていると「ちょっと知っている人」ぽくは見えたりしますので、是非頭の片隅に入れておいていただければと思います。