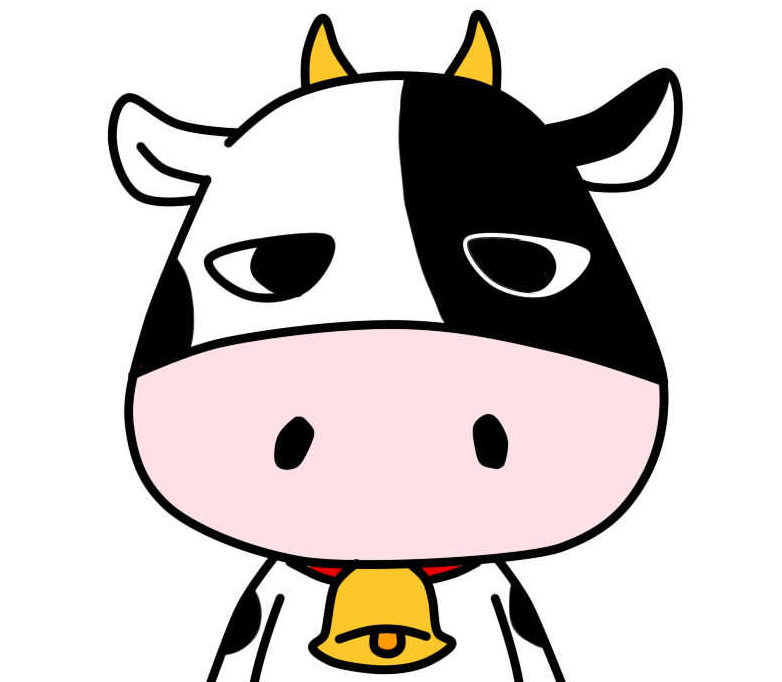私たち現代人が日常的に食べている牛肉ですが、健康や体型を気にしている方にとっては「牛肉ってどんな栄養素があるんだろう」「体にいいのかな?」と思うことも多いかと思います。
そこでこの記事では「牛肉の栄養」にフォーカスをあてて、実際にどんな栄養素が入っていて、体にどんな影響を与えるのか、また気になるカロリーなどに関してもお伝えしていければと思います。
牛肉の栄養を一言で言うと

「牛肉」と聞くとどんなイメージが浮かんできますか?脂身が多いし、高カロリーでダイエットには大敵…という感じでしょうか。
確かにお肉には太るというイメージがありますが、驚いたことに牛肉は非常に効率のよい健康食品でもあります。
牛肉には、例えば糖質や脂質の代謝に関わるビタミンB群や鉄分。また特に赤身には動物性たんぱく質など、男女を問わず健康に欠かせない栄養素がたっぷり含まれています。
このように一般的なイメージとは反対に、牛肉は体にいい上にダイエットにも役立つ優れた栄養素を持つ食品なのです。
牛肉に含まれる代表的な栄養素
牛肉に含まれる代表的な栄養素は以下の6つです。聞いたことがある栄養素もあれば、初めて耳にする栄養素もあるかと思いますが、どれも人間の体には欠かせない大切な栄養です。
・たんぱく質
・ヘム鉄
・ナイアシン
・ビタミンB12
・亜鉛
たんぱく質_必須アミノ酸が含まれる

牛肉や豚肉に含まれる「動物性たんぱく質」には、体内で作ることのできない「必須アミノ酸」がバランスよく含まれています。
この必須アミノ酸のうちどれか1つでも欠けてしまうと、肌荒れや肝機能の低下、アレルギー症状、脳や神経の機能の低下、疲れが取れにくいなど、さまざまな不調をきたすことになり、重大な栄養障害を引き起こす可能性もあるのです。
よく大豆などの植物性たんぱく質が健康に良いと言われますが、アミノ酸のバランス(アミノ酸スコア)という点では、実は動物性たんぱく質のほうが優れています。
植物性タンパク質よりも優れた動物性タンパク質

牛肉などに含まれる動物性のたんぱく質は、植物性のものよりもより効率的に吸収されやすいので、筋肉をつくり代謝を上げる効果も期待できます。
牛肉に含まれているたんぱく質は、人体に大切な必須アミノ酸をバランスよく含むだけでなく、調理による損失がほとんどないうえに、体内で吸収されやすいという特徴をもっています。
また、動物性たんぱく質は免疫力を高める効果も持ち合わせています。中でもリンパ球のNK(ナチュラルキラー)細胞は、ガン細胞やウィルスに感染した細胞を排除し、とくにガンの転移を抑制する働きがあると注目されています。
さらにお肉のたんぱく質は、豆や魚介類、卵、牛乳などのたんぱく質よりもNK細胞を活性化するという報告もあります。
たんぱく質は骨や筋肉、血液を作る材料になるので、高齢の方がお肉をたくさん食べることで筋力の低下を抑えることができ、転倒や骨折を防ぐことにもつながります。
ヘム鉄|驚異の鉄分量

血液の成分であるヘモグロビンを作るために欠かせない栄養素が「鉄分」ですが、私たちの体内では作ることができません。そのため、食事から鉄分を摂取しないと貧血になってしまう可能性もあります。
そんな貧血予防に効果的なのが、牛肉や豚肉などの食肉に含まれる「ヘム鉄」です。牛肉には、豚肉や鶏肉の3~4倍もの鉄分が含まれています。
鉄分は貧血に限らず、手足の冷えや枝毛などの予防、酸素を全身に送り疲れにくい体をつくることにも効果的です。
牛肉に含まれるヘム鉄は、植物性食品に含まれる非ヘム鉄分よりも、5~10倍も吸収性が高いといわれています。さらに、非ヘム鉄の吸収率も高めてくれるので一石二鳥です。
鉄分の吸収を高めるにはビタミンCと一緒に摂ることが効果的なので、付け合わせにサラダやポテトを食べるのがおすすめです。
脂肪代謝にも効果のあるナイアシン
ナイアシンはビタミンB群の仲間で、細胞でエネルギーを生産する際に働く酵素を助ける働きをします。つまり、皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きを助けている、ということです。
脂肪代謝にも関わりがあり、中性脂肪やコレステロールを減らす作用があるとされています。アルコールを分解してくれるので、二日酔いの予防にも有効です。
また、心の不調、うつや統合失調症に効くことが期待されています。
造血ビタミン→ビタミンB12

ビタミンB12は子供や女性、高齢の方には特に欠かせない栄養素のひとつです。エネルギーの生産を促進し、記憶力を高める、月経異常を防ぐ、精神のバランスを安定させるといった働きがあります。
「造血ビタミン」とも呼ばれるビタミンB12は、葉酸と協力して血液を増やすための合成を助け、貧血になるのを防いだり、顔色をよくしたり、髪の毛を艶やかにするなどの作用があります。
また神経との関係が深く、脳からの指令を伝える神経を正常に保つという役割もあります。脳の正常な働きをサポートし、うつ状態やアルツハイマー病の予防に有効な栄養素と言われています。
不足しがちな亜鉛

最近はダイエットの影響や、インスタント食品のとり過ぎで亜鉛不足になる人が多いそうです。
亜鉛には細胞分裂や新陳代謝を促す働きがあるため、適量を摂取することで免疫細胞が活性化し、免疫力を高める効果が期待できます。
感染症や病気の予防には、免疫力アップが不可欠です。亜鉛は細胞の新陳代謝に必要な大切な栄養素なのですが、体内では作ることができません。
牛肉には他のお肉に比べて亜鉛が豊富に含まれています。牛肉を100g食べるだけで、なんと一日の摂取目安量の半分を補うことが出来ます。
細胞の生まれ変わりに関係していることもあり、亜鉛が不足すると味覚障害など様々な問題が生じてきます。
部位別の栄養の特徴はあるのか?

さてここまでご説明してきた通り、牛肉には様々な栄養素が含まれています。しかしこれらの栄養素がどこの部位でも同じだけ含まれているわけではありません。
続いては、その栄養素の部位別の特徴を解説します。
栄養素を取るには最も適した部位が赤身肉

「たんぱく質」「鉄」「ビタミンB」という、健やかな美肌づくりに重要な三大栄養素をもれなく、効率よくたくさん摂るには赤身肉が一番です。量は1日150~200gでOKです。
赤身肉の一番のポイントは、脂肪燃焼を促すL-カルニチンが豊富に含まれていることです。
また、赤身には先ほど説明した「ヘム鉄」と呼ばれる鉄分が多く含まれています。身体への吸収率にとても優れた栄養素です。赤血球がつくられるときに必要なビタミンB12が豊富なのも特徴です。
さらに、赤身肉には必須アミノ酸のトリプトファンも多く含まれています。トリプトファンからつくられるセロトニンは、その一部が脳神経に含まれていて、不足するとうつ病などの脳の病気を引き起こす原因となります。
赤身肉を摂ることは、うつ症状の改善、脳の健康維持にも大切です。

脂肪が豊富なので少し注意して食べたいのがロース


牛の背中の肉をロースと言います。うまみが多く高価な部位ですが、脂肪がかなり多いので、ダイエットや生活習慣病予防の点からは気になるところです。
肉類の脂質は、取り過ぎると余分なコレステロールとして内臓や血管、皮下に蓄積してしまい、生活習慣病の原因となるので注意が必要です。
しかし一方では細胞膜をつくったり、血液・ホルモンなどの原料となったり、ビタミンA・D・Eなどの吸収を助けるなど重要な働きをしています。
体の発育や生命の維持に不可欠なものなので、適切な量の摂取は欠かせません。
カロリーがちょっと高めなことに気をつければ、高たんぱく質で「ビタミンB1」や「カルニチン」といった成分も多く含まれているので、ダイエット中にもおすすめの食材です。
焼肉の定番バラ肉(カルビ)


バラ肉とは、腹側についている肉のことで、とても脂肪の多い部位です。焼肉で人気のカルビがここに分類されます。一価不飽和脂肪酸と亜鉛が豊富に含まれていることが特徴です。
一価不飽和脂肪酸は、飽和脂肪酸の代わりに摂ると、動脈硬化の原因となる悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らし、動脈硬化の防止に役立つ善玉コレステロール(HDLコレステロール)は減らさないという性質があります。
この脂肪酸は、体にいいと人気のオリーブオイルに含まれているオレイン酸と同じ成分です。
牛肉ダイエットは可能?牛肉のカロリーについて(部位ごとに)


「痩せたい人こそお肉を食べましょう」と言われるようになって久しいですが、お肉を食べて痩せられるなら、こんなに嬉しいことはありません。
実際に牛肉を食べてダイエットなどすることができるのでしょうか?
牛肉といえば他のお肉に比べてカロリーが高いイメージがありますが、実はそれがかえってダイエットに向いているとも言えるのです。
牛肉がダイエットに向いている理由
なぜかと言うと、例えば牛肉の脂質が多い部位でいうと、確かにカロリーは高いのですが、高脂質なためとても腹持ちが良いからです。
腹持ちが良いと、自然と次の食事や間食が軽くなり、必然的に一日の食事の量が少なくなります。これがダイエットにいいと言われる理由のひとつです。
ダイエットには、脂肪燃焼効果を高める成分「カルニチン」を多く含むヒレもオススメです。
また、牛肉にはロイシンという成分も多く含まれており、筋肉増強効果が期待できます。筋肉が増えると体の基礎代謝がよくなるので、エネルギーを消費しやすくなり、太りにくく痩せやすい体になります。
部位別!牛肉の部位別カロリー


気になるカロリーを部位別に見てみると、次のようになります。
・肩、脂身付_286kcal
・肩、皮下脂肪なし_265kcal
・肩ロース脂身付_411kcal
・肩ロース皮下脂肪なし_403kcal
・バラ_517kcal
・もも脂身付_246kcal
・もも皮下脂肪なし_220kcal
まとめ
食生活が欧米化したことで肥満や生活習慣病が増えていると言われることもあり、肉食にはあまり良くないイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、これまで見てきたように、牛肉は部位を選んで食べると非常に健康にいい食材でもあるのです。
ぜひヘルシーなお肉選びのポイントを知り、健康づくりに役立てていきましょう。